導入文
「寝返りのたびに肩がズキッとして眠れない」
「腕が横にも前にも上がらない。服を着るのもつらい」
「リハビリと注射を続けているのに、半年たっても良くならない」
いわゆる五十肩(凍結肩)は、時間が経てば治る——そう言われがちですが、“放置して自然回復”が難しいケースも確実に存在します。とくに夜間痛が強い/可動域が著しく制限/6ヶ月以上改善が乏しいなら、肩だけでなく肩甲骨・胸郭・頸椎・体幹、さらに代謝(血糖)やストレスまで含めた“全体の見直し”が必要です。
この記事では、一般的な「肩のマッサージや注射」だけでは抜け出せない理由と、肩に負担が集中しない体の使い方を取り戻す道筋を、専門的だけど分かりやすく解説します。
なぜ良くならない?——五十肩を長引かせる“3つの見落とし”
1) 肩そのものより「肩甲骨と胸郭」が動いていない
腕を上げる動きの約3〜4割は肩甲骨と肋骨(胸郭)の連動です。ここが硬いと、上腕骨の関節包だけにストレスが集中し、炎症→痛み→さらに動かさない…の悪循環に。
- 胸を丸めてデスク作業が多い
- 猫背で肩が前に巻いている→ 肩甲骨が肋骨の上を“滑れない”ため、関節包がいつまでも引きつれます。
2) 首・神経の“過敏化”がブレーキになっている
痛みが続くと首〜肩の神経が過敏になり、わずかな動きでも痛み信号が過剰に出ます。結果、防御的に筋肉が硬直→可動域ダウン。
- 首を動かすと肩の奥がズキッとする
- 夜間、うずきで目が覚める→ 神経の興奮を落とす“やさしい動かし方”が必要です(強いストレッチは逆効果)。
3) 代謝・ホルモンの影響(体の内側の問題)
血糖コントロール不良(糖質過多)や甲状腺機能の乱れは、関節包の線維化(固まりやすさ)に関与し、治りを遅らせます。
- 夜甘いものやお酒が多い
- 朝だるくて動き出しが重い→ 食事タイミングと栄養素の見直しが、炎症を鎮める近道です。
悪化させない動かし方——“やってはいけない”と“今日からのコツ”
やってはいけないこと
- 限界までの強いストレッチ「痛いほど伸ばす」は線維化を進め、夜間痛を悪化させます。
- 背中で手を組む・急な万歳動作関節包を一気に引きつらせます。リハビリ段階でも最後に回す動き。
- うつ伏せ腕上げ・フォームローラーの強圧前肩・首の過緊張を誘発しがち。
- 長時間の同一姿勢(PC・スマホ俯き)肩甲骨が固まり、痛みのスイッチが入りやすくなります。
今日からのコツ(1回3〜8分、朝・夕の2セット目安)
- ペンデュラム(コッドマン)30〜60秒×2体を前に軽く傾け、痛い側の腕は“重りのようにぶら下げる”。小さな円を心地よい範囲で。→ 関節内圧を下げ、夜間痛の鎮静に有効。
- 肩甲骨セット 5呼吸×2座位で背もたれに軽くもたれ、肩をすくめずに“下げて・わずかに後ろへ”。→ 肩甲骨が肋骨上で“滑る”感覚を回復。
- 胸郭ひらき(タオル胸椎サポート)60秒タオルを丸めて肩甲骨の間に置き、鼻4秒吸う→口6秒吐くを繰り返す。→ 猫背を中立へ。腕上げの余裕づくり。
- ハンズテーブル(痛み0〜2/10内)10回×2テーブルに両手を置き、お腹を少し引き込みながら体を前へスライド=結果として腕が前上り。→ “肩だけ”でなく体幹ごと動かす練習。
- 外旋スライド(タオル挟み)10回×2脇に小タオルを挟み、肘90°で**外向きへ“数センチ”**滑らせ戻す。痛みが出ない範囲で。→ 回旋腱板(インナーマッスル)を安全に再起動。
- 就寝ポジション調整(夜間痛対策)痛い側を上にして横向き。脇に枕(厚め)を挟み、腕を少し前へ。仰向け時は肘下にクッションで肩前方の牽引を減らす。
1日の運用ルール
- 痛みスケールは“2/10以内”で止める(翌日に残る痛みはNG)。
- 1時間同一姿勢ごとに60秒の肩甲骨セット+胸式→腹式の切り替え呼吸。
- 温めは入浴10分→エクササイズの順が効率的(急な熱感は冷却5〜10分)。
- 進捗は**「上着を着る動き」「髪に触れる高さ」**など日常動作で記録(週1)。
改善ロードマップ——「痛み鎮静 → 可動回復 → 機能復帰」の3フェーズ
いちどに全部はやりません。段階を守るほど早く安全に戻れます。
フェーズ1|痛み鎮静(目安:2〜6週)
目的:夜間痛を落とし、“動かせる土台”を作る
- やること
- ペンデュラム(30〜60秒×2〜3回/日)
- 肩甲骨セット(5呼吸×2、1〜2時間おき)
- 胸椎タオルポジションで呼吸(60〜90秒×1〜2回/日)
- 外旋スライド(痛み0〜2/10、10回×2)
- 就寝ポジション(脇枕+肘下クッション)
- やらないこと
- 限界ストレッチ、背中で手を組む、強圧マッサージ
- 次フェーズへの合図
- 夜間痛が3/10以下
- Tシャツが痛みを我慢せず着られる
- 机の上で肘が楽にスライドできる
フェーズ2|可動回復(目安:4〜12週)
目的:固まった関節包を“安全に”広げる
- やること(各10回×2、痛み0〜3/10内)
- テーブルスライド(前方・斜め45°):体幹を前に送って、結果的に腕が上がる
- ウォール・スライド:壁に前腕を当て、肩をすくめずゆっくり上へ
- 外旋レンジ強化:タオルを脇に挟み、外向きへ数センチ→戻す
- 胸郭モビリティ:椅子に座り、胸骨をそっと上に(反りすぎない)
- 肩甲骨の滑走:肩を軽く「下げて・わずかに後ろ」→5呼吸
- コツ
- 「痛気持ちいい一歩手前で止める」
- 呼吸は吸う4秒/吐く6秒、吐く時に可動域が少し広がる感覚を探す
- 次フェーズへの合図
- 前方挙上(前にならえ)が肩の高さを超える
- 外旋(肘90°)が体幹に触れたタオルを落とさず10回できる
- 夜間痛が2/10以下で連続3日
フェーズ3|筋力・機能復帰(目安:8〜16週〜)
目的:再発しない“使い方”と力を取り戻す
- やること(週3〜4回、各10回×2)
- 等尺性ローテーターカフ:ゴム帯を弱めに、痛み2/10内で外旋・内旋
- 前鋸筋アクティベーション:壁プッシュで肩甲骨を前に滑らせる
- 肩甲骨ヒンジ:軽ダンベル(0.5〜1kg)ですくめず下制を保つ
- 日常動作リハ:上棚に軽い物を出し入れ、上着の着脱をゆっくり反復
- 進め方
- 重量よりフォーム:痛みが翌日に残るなら負荷を戻す
- 2週ごとに回数+2または抵抗ほんの少しUPのどちらかだけ
- “卒業”の目安
- 就寝・起床・日中とも痛み0〜1/10が1〜2週間続く
- 肩の高さ+30°までスムーズに挙上
- 上着着脱・洗髪・後ポケット動作が怖くない
フェーズ共通のリスク管理(いつでも立ち戻れる“安全スイッチ”)
- 痛みが3/10を超えたらその場で呼気を長く(6〜8秒)+可動域を2割縮小
- 夜間痛が増えた日は、翌日をフェーズ1メニューに戻す
- 次の症状は受診目安:発熱を伴う強い痛み、肩の赤み・腫れの増大、外傷後の急な可動域喪失、明らかな筋力の脱落
このロードマップどおりに**“痛みを抑えながら、少しずつ可動域と使い方を取り戻す”**のが最短距離です。まとめ|「時間が解決する」は、誤解です
五十肩・四十肩は、ただの“肩の炎症”ではありません。
体の動き・神経・代謝が絡み合う全身のバランスの乱れが、長期化の原因です。
時間が経てば治る人も確かにいます。
しかし、**6ヶ月以上痛みが続く人の多くは“自然回復しないパターン”**に入っています。
「我慢していればいつか…」ではなく、
- 肩甲骨と胸郭の動きを取り戻す
- 神経の興奮を落ち着かせる
- 内側から炎症を抑える栄養バランスを整える
これらを丁寧に積み重ねることで、夜の痛み・可動域・日常動作が少しずつ変わっていきます。
整体院導では、肩だけに注目するのではなく、**“肩が痛くならない構造を再設計する”**アプローチを行っています。
「寝返りで痛い」「服を着るだけでつらい」
そんな状態から抜け出すために、あなたの体を根本から見直す第一歩を踏み出してみてください。

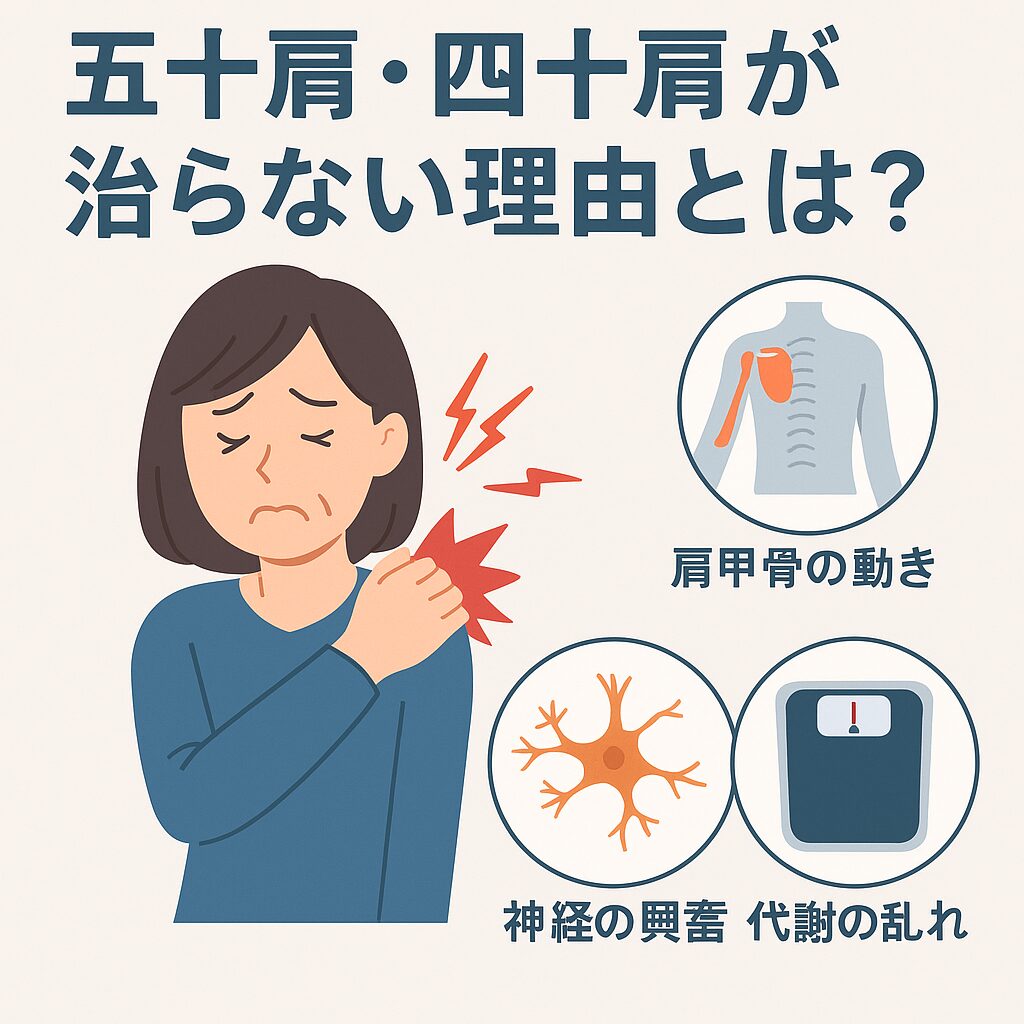
コメント