導入文
耳鼻科の検査は異常なし。薬を飲んでも良くならない。
ふと顔を動かした瞬間や、PC作業のあとにフワッと浮く感じ・ぐらつきがぶり返す——。
それ、**首(頸椎)と自律神経の乱れが関わる「頸性めまい」**の可能性があります。
首の筋膜・関節がこわばると、目・耳・体のセンサー(平衡感覚)の統合が狂い、
「回転というより“フワフワ”“船に乗った感じ”」が続きやすくなります。
この記事では、一般的な内耳性めまいとは違う頸性めまいの見抜き方と、
首・目・呼吸を同時に整える再発させない実践ステップを、わかりやすく解説します。
こんな人は“頸性”を疑うサイン
- 首や肩こりが強い日にふらつきが増える
- 上を向く/振り向くと不安定感が出やすい
- まぶしい画面・人混みで視覚刺激に弱い
- 朝より夕方に悪化、睡眠が浅い・歯ぎしりがある
- 乗り物酔いしやすい/首のケガ・むちうち歴がある
なぜ首で“めまい”が起きるのか
── 平衡感覚をつかさどる「3つのセンサー」がズレるから
私たちがまっすぐ立てているのは、
脳が3つのセンサー(目・耳・首)からの情報を統合してバランスを保っているからです。
- 視覚(目):空間と地平線の位置をキャッチ
- 前庭器官(耳):体の傾き・回転を検知
- 深部感覚(首):頭の位置と動きを検出
このうち、**首の深部感覚(頸部固有受容器)**が乱れると、
「頭の位置情報」だけズレて脳が混乱します。
結果、目や耳の情報との整合性が取れず“めまい感”を錯覚的に感じるのです。
1. 姿勢の崩れと筋膜のこわばり
スマホ・デスクワーク姿勢が長いと、
首前面の筋膜(胸鎖乳突筋)・後面の筋膜(後頭下筋群)が硬直し、
頭の傾きセンサーが誤作動します。
この“情報のズレ”がフワフワ感・視界の揺れにつながります。
2. 呼吸の浅さによる自律神経の乱れ
緊張が続くと呼吸が浅くなり、交感神経が優位に。
血流が低下して首のセンサーがさらに過敏化します。
その結果、**「めまい+肩こり+頭痛+不眠」**がセットで出やすくなります。
3. 眼球運動との協調不全
首の深部筋群(特に後頭下筋群)には眼球の動きと連動する受容器が存在。
首が硬く動かないと、目のピント調整や追視が狂い、
**「目がチカチカする」「視界が流れる」「人混みでクラクラする」**などの症状が出ます。
💡ポイント:
「耳の異常がないのにフワフワする」場合、
実際は首のセンサーと自律神経がずれているケースがほとんど。
めまい薬では“感覚のズレ”までは修正できないのです。
なぜ首で“めまい”が起きるのか
── 平衡感覚をつかさどる「3つのセンサー」がズレるから
私たちがまっすぐ立てているのは、
脳が3つのセンサー(目・耳・首)からの情報を統合してバランスを保っているからです。
視覚(目):空間と地平線の位置をキャッチ
前庭器官(耳):体の傾き・回転を検知
深部感覚(首):頭の位置と動きを検出
このうち、**首の深部感覚(頸部固有受容器)**が乱れると、
「頭の位置情報」だけズレて脳が混乱します。
結果、目や耳の情報との整合性が取れず“めまい感”を錯覚的に感じるのです。
1. 姿勢の崩れと筋膜のこわばり
スマホ・デスクワーク姿勢が長いと、
首前面の筋膜(胸鎖乳突筋)・後面の筋膜(後頭下筋群)が硬直し、
頭の傾きセンサーが誤作動します。
この“情報のズレ”がフワフワ感・視界の揺れにつながります。
2. 呼吸の浅さによる自律神経の乱れ
緊張が続くと呼吸が浅くなり、交感神経が優位に。
血流が低下して首のセンサーがさらに過敏化します。
その結果、**「めまい+肩こり+頭痛+不眠」**がセットで出やすくなります。
3. 眼球運動との協調不全
首の深部筋群(特に後頭下筋群)には眼球の動きと連動する受容器が存在。
首が硬く動かないと、目のピント調整や追視が狂い、
**「目がチカチカする」「視界が流れる」「人混みでクラクラする」**などの症状が出ます。
💡ポイント:
「耳の異常がないのにフワフワする」場合、
実際は首のセンサーと自律神経がずれているケースがほとんど。
めまい薬では“感覚のズレ”までは修正できないのです。
性めまいを“繰り返さない”ための再発予防アプローチ
めまいは一度落ち着いても、再発しやすいのが特徴です。
特に首まわりの筋膜・神経・血流が慢性的に乱れていると、
天候・ストレス・睡眠不足などの小さなきっかけでぶり返します。
ここでは、再発を防ぐために整体院導が実際に行っている3つの根本アプローチを紹介します。
① 構造の再設計:首だけで支えない体づくり
首に負担が集中するのは、骨盤・背骨・肩甲骨のバランスが崩れているから。
導ではまず、全身の構造を立体的に整え、**“首が頑張らなくても立てる体”**をつくります。
- 骨盤と背骨のねじれを3D評価
- 背骨のS字カーブと重心軸を再構築
- 座り方・立ち方・歩行のクセを修正
この段階で、首の過緊張と血流不足が大幅に改善し、
めまい発作の頻度が半減するケースも少なくありません。
② 感覚の再教育:首・目・呼吸の連動トレーニング
頸性めまいは「目」と「首」の情報ズレが根っこ。
導では視覚・体性感覚・呼吸を同時に整える再教育を行います。
- 眼球運動と首の連動性を高めるリハビリ
- 呼吸と体幹をつなぐ神経反射トレーニング
- パワープレートを活用した“感覚リセット”運動
これにより、動いても揺れない安定感が戻ります。
③ 超栄養学による神経回復サポート
めまいを慢性化させる大きな要因の一つが、神経・血管の回復力の低下。
導では、最新の超栄養学に基づいて、神経を修復しやすい体内環境を整えます。
- ビタミンB群・マグネシウム・鉄分などの神経代謝サポート
- 炎症を抑えるオメガ3・抗酸化食材の提案
- 甘いもの・カフェイン過多による交感神経緊張の改善
外から整えるだけでなく、内側から“再発しにくい神経”を育てる。
これが、薬に頼らず長く安定するための鍵です。
整体院導での専門アプローチと実際の流れ
1. ヒアリングと赤旗チェック(約10分)
めまいの出方、時間帯、首肩のコリ、睡眠やストレス、服薬状況を確認。危険な兆候(激しい頭痛、ろれつ困難、麻痺、意識障害、聴力の急変など)があれば提携医療機関の受診を優先します。
2. 頸性スクリーニング(約15分)
- 首の可動と症状変化(上向き、振り向き、うなずき)
- 眼球運動と首の連動テスト(目だけ動かす/首だけ動かす)
- 肩甲帯・胸郭の可動、呼吸の深さ
- 立位バランス(開眼・閉眼)、歩行時のふらつき→ めまいを引き起こす「動きの組み合わせ」を特定します。
3. 構造の整備(約15分)
- 肩甲骨と肋骨の滑りを回復(痛みのない可動域で)
- 胸椎の丸まり過多を中立へ(タオル支持+優しい動き)
- 骨盤・足部のアライメントを微調整し、首だけで支えない姿勢を作る
4. 感覚の再教育(約10分)
- 首の深部筋を目と協調させる“うなずき微運動”
- 追視(目で追う動き)と頸の微小回旋を同期
- 呼気を長くして自律神経を安定(吸う4秒/吐く6〜8秒)
5. パワープレート活用(適応者・約5分)
- ごく低振動で下半身から感覚入力を整え、上半身の過敏を下げる
- 目と首の協調を保ったまま、短時間で全身のバランスを刺激
6. 自宅プログラムの処方(3〜5分)
- 朝:うなずき微運動+呼吸1分
- 日中:肩甲骨セット20秒を2〜3回
- 夜:首前面の温め2〜3分→呼気ゆっくり※ 痛みや強いふらつきは2/10を超えない範囲。悪化日には量を半分に。
7. 進捗の見える化(毎回30秒)
- めまいの強さ(0〜10)、発作回数、画面や人混みでの耐性を記録
- 首の回旋角度(左右)と「フワッ」の出方をメモ→ 1〜2週で客観的に変化を確認します。
来院目安と安全ライン
- 目安:初期は週1、2〜4回で「日中のフワフワ感が軽い」を目標
- 中止・受診目安:激しい頭痛、ろれつ困難、片側の脱力・しびれ、聴力急変、嘔吐を伴う増悪
まとめ|“耳は正常なのにフワフワ”の正体は、首と自律神経のズレ
・耳鼻科で異常なしでも、首(頸部の深部感覚)と自律神経がずれると「フワフワ・ぐらつき」は起きます。
・首だけをもむより、肩甲骨・胸郭・骨盤までの構造、目と首の協調、呼吸(自律神経)を同時に整えることが再発予防の近道。
・まずは1分セルフチェック(首の回旋/眼球運動/押圧反応/呼気を長く)→ 初期ケア(うなずき微運動・温め・長い呼気)で“ズレ直し”を。
・不安定感が続く、夜間の不眠や頭痛が伴う、動作で悪化する——そんな時は、上流から下流まで一気通貫で評価し直す価値があります。整体院導では「構造×感覚(首・目)×超栄養学」で、ぶり返さない土台づくりを行います。
HP → https://michibiki-seitai.com/
LINE(症状別改善方法を無料プレゼント!) → https://liff.line.me/2006347044-kjWb9VWB/landing?follow=%40075zodjf&lp=ICDzSQ&liff_id=2006347044-kjWb9VWB

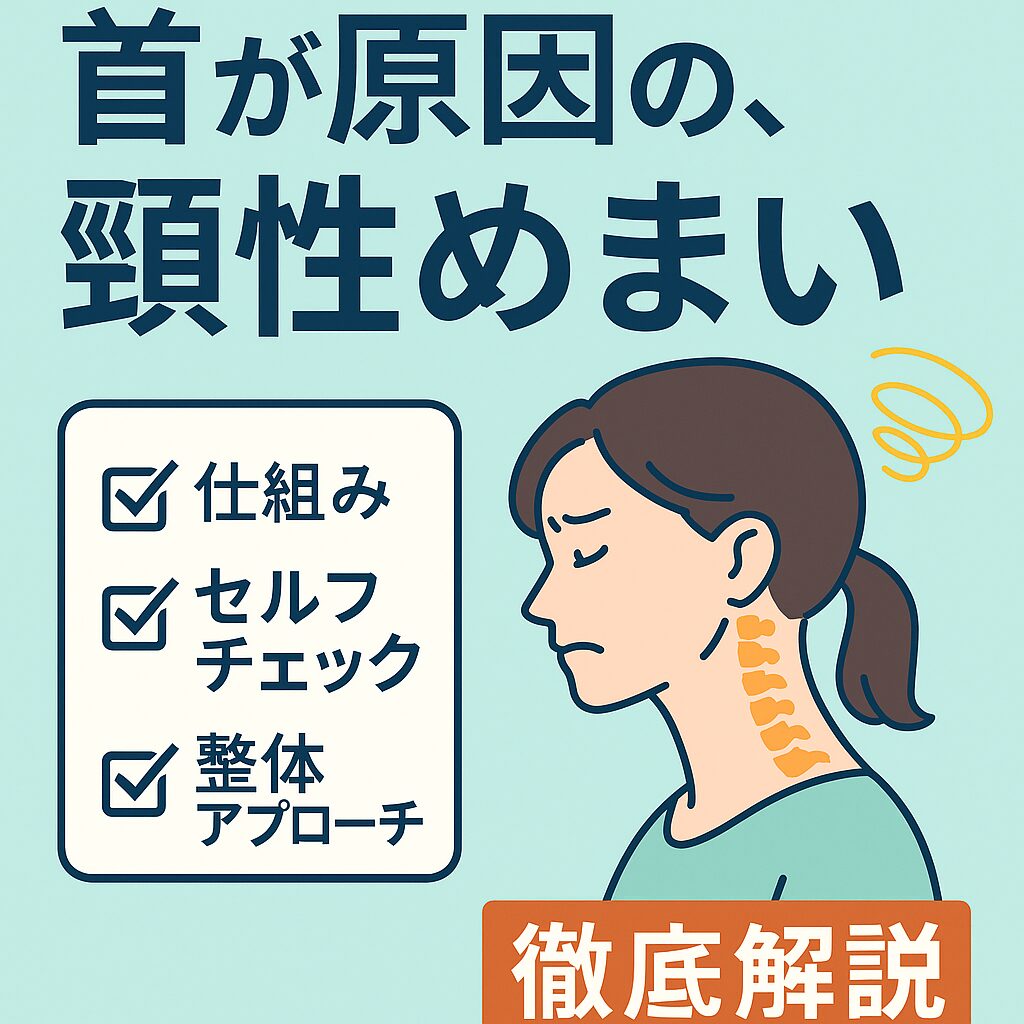
コメント