「最近、歩き始めに股関節が痛い…」
「変形性股関節症と診断されたけど、原因がよくわからない」
そんな方へ。この記事では、変形性股関節症の真の原因を、骨・筋肉・神経の3つの視点から分かりやすく解説します
受診のサイン:この症状がある人は変形性股関節症を疑って
「最初の一歩がズキンとする」
「階段の昇り降りで足の付け根に違和感がある」
「長時間座っていると、立ち上がりで股関節が固まったようになる」
そんな経験はありませんか?
これらのサインは、**初期の変形性股関節症(OA)**に共通して現れることが多い症状です。
特に、以下のような方は早めの専門的な評価が必要です。
よくある初期症状チェックリスト
- 歩くときに足を引きずるクセがある
- 靴の外側ばかりすり減っている
- 動き始めに痛みがあるが、しばらく動くと和らぐ
- 股関節の可動域(開き)が左右で違う
- 夜間痛やじっとしていても違和感を覚える
これらの症状は、単なる「筋肉痛」や「加齢のせい」ではなく、股関節の変性によるサインである可能性があります。
なぜ早期発見が重要なのか?
変形性股関節症は、初期段階で適切な対処を行えば、進行を食い止める・遅らせることが可能な疾患です。
しかし見過ごしてしまうと──
軟骨が徐々にすり減り、骨と骨がぶつかるようになり、人工関節手術を勧められるほど重度化してしまうケースも珍しくありません。
「歳のせいかも…」「もう少し様子を見よう」
そう思っている間にも、関節へのダメージは進行していきます。
早期に「本当の原因」を突き止めることが、痛みの緩和と未来の歩行を守るための第一歩になります。
そもそも“変形”とは何か?──レントゲンだけで判断してはいけない理由
「先生、レントゲンで“変形してますね”って言われました…」
多くの方がこの一言で、「もう治らないんだ…」と落ち込んでしまいます。
でもちょっと待ってください。
本当に「変形=痛み」なのでしょうか?
レントゲンの限界:写るのは“骨の形”だけ
レントゲンで確認できるのは、骨のすき間(=軟骨の厚み)や形状、骨棘(こつきょく)と呼ばれるトゲのような変化です。
しかし、そこには写らないものがたくさんあります。
たとえば…
- 筋肉のバランス
- 神経や血管の状態
- 関節の滑らかな動き(滑走性)
- 荷重時の関節面の当たり方
つまり、痛みの本質的な原因はレントゲンでは見えないことが多いのです。
「無症候性OA」──変形していても痛くない人がいる理由
実際、変形性股関節症の所見があっても「まったく痛みがない人」もいます。
こうした状態は「無症候性OA(症状のない関節変形)」と呼ばれ、海外論文でも多数報告されています。
逆に、レントゲンでは軽度でも、日常動作のクセや股関節周囲の筋の使い方によって痛みが強く出るケースも多いのです。
大切なのは「動的評価」
静止した状態だけを見て「変形ですね」で終わってしまうと、治療の方向性を誤ることも。
本当に見るべきは、立った時・歩いた時・階段昇降など動作時に股関節がどう使われているかです。
私たちは、**レントゲンに写らない“動きのエラー”や“荷重の偏り”**にこそ注目して根本改善を目指しています。
原因①:股関節に“過剰な圧”がかかる体の使い方
股関節は本来、骨盤と太ももをつなぐ“球関節”であり、滑らかに回旋しながら動く構造になっています。
しかし、現代人の生活習慣によって、その滑らかな動きが損なわれ、関節に過剰な「圧(コンプレッション)」がかかる体の使い方をしている人が非常に多いのです。
「つま先重心」で股関節がロックされる
例えば、立っているときや歩いているときに「つま先に重心が乗りやすい」人は要注意。
この姿勢は体の前方へ荷重が偏り、股関節の前面が常に詰まった状態になります。
この状態が続くと…
- 関節内圧が上昇し
- 股関節の滑りが失われ
- 骨と骨の接触ストレスが増える
つまり、“動かしながら壊している”という状態に近づいていくのです。
「足指が浮いている」ことが原因になることも
地面にしっかり足指が接地していない(浮指)と、バランスを保つために過度に股関節周囲の筋肉を緊張させる必要が出てきます。
その結果、股関節の圧縮力が高まり、軟骨の摩耗が加速するのです。
痛みの原因は“動き方の癖”にある
変形性股関節症が進行する人の多くは、**「体の構造的な歪み」+「悪い動きのクセ」**を持っています。
つまり「骨が悪い」のではなく、「使い方が間違っている」ことが大半です。
関節の変形に至るまでには、日々の積み重ねられた“動作エラー”の連続があるのです。
原因②:骨盤のゆがみと股関節の“かばい歩行”
「昔、ぎっくり腰をやってから歩き方が変わった気がする」
「右の股関節が痛くて、左に体重を乗せて歩いている」
そうした経験はありませんか?
実は、痛みを避けようとする“かばい動作”そのものが、変形性股関節症の悪化を招いているケースが非常に多く見られます。
骨盤がズレると「脚の長さ」に差が出る
骨盤の左右のバランスが崩れると、股関節の位置関係もズレてきます。
この影響で、実際に脚の長さが変わることはなくても、片足が長く・もう一方が短く“感じる”歩き方になってしまうのです。
すると…
- 長く感じる方の足は“引きずる”ような動作になり
- 短く感じる方の足は“着地が強く”なり
- 股関節や膝への負担に左右差が生まれる
この非対称な荷重が、軟骨や関節唇へのダメージを蓄積していきます。
かばい歩行は“正常な関節運動”を阻害する
かばいながら歩くことで、股関節の自然な回旋運動が減少し、前方・後方の滑走性が失われます。
これが結果的に、摩耗しやすい部分にストレスが集中し、「前だけがすり減る」など偏った変形パターンが形成されます。
動作と構造は連動している
たとえば、骨盤が後傾していると、股関節は詰まりやすく、後ろに引きづらくなります。
逆に骨盤が前傾しすぎると、股関節の前側に圧縮ストレスが集中します。
つまり、骨盤の位置が変われば、股関節の動きも変わる。
それによって、痛みや変形の進行スピードにも大きな差が出てくるのです。
原因③:インボディでわかる“筋力とむくみ”の関係
変形性股関節症の痛みや変形の進行において、「筋力低下」や「むくみ」が大きな要因になっていることをご存じでしょうか?
当院ではInBody(インボディ)という精密測定機器を使用して、体の状態を数値化しています。
この測定により、「どの部位の筋力が落ちているか」「体液バランスに異常がないか」などが詳細にわかります。
太ももの筋力が落ちると“関節の安定性”が失われる
特に注目すべきなのは、**大腿四頭筋(前もも)や中臀筋(お尻横)**の筋力低下。
これらの筋肉は股関節を安定させる「スタビライザー」の役割を果たしています。
InBodyで数値的に低下が見られる場合、実際の動作でも以下のような影響が現れます:
- 歩くときのふらつき
- 片足立ちが不安定
- 階段昇降でのガクッと感
これらは全て、股関節への過剰な負担のサインです。
むくみ=細胞がうまく代謝できていない状態
InBodyでは、体水分バランスの異常も検出できます。
脚がむくんでいる=静脈やリンパの流れが滞っているということ。
これは老廃物の代謝が低下し、関節周囲に慢性的な炎症物質がたまりやすくなっている状態でもあります。
慢性炎症は、関節の痛みを長引かせる一因にもなるため、むくみの改善も治療の一部と捉える必要があります。
「筋力が落ちているかどうか」だけでは足りない
筋力というのは“ただある”だけでは意味がありません。
どのタイミングで・どの方向に・どれだけの強さで使えるかが重要です。
つまり、「筋力の質」まで見て判断することが、変形性股関節症の改善には不可欠なのです。
“今日からできる3つの対策”──ただし自己流は危険
変形性股関節症を改善・予防するうえで、「今日からでも取り組める」ことは確かにあります。
しかし、自己流で行うと逆効果になることも少なくありません。
ここでは、医療や運動学の知見に基づいた「安全な3つの対策」をご紹介します。
① 股関節を圧迫しない座り方に変える
座っている時間が長い人ほど、股関節が詰まりやすい体勢になっています。
とくに、柔らかいソファやあぐら姿勢、脚を組むクセがある方は要注意です。
おすすめは「軽く浅めに腰掛け、足裏をまっすぐ床につける」こと。
この座り方は、骨盤を立てて股関節への圧力を逃がすことができ、長時間の負担を軽減します。
② 靴を見直して「足元の衝撃」を減らす
硬すぎる靴底や、足に合わない靴は、歩くたびに股関節へダイレクトな衝撃を与える要因になります。
特に以下の点をチェックしてください:
- 中敷きがすり減っていないか
- 指先が窮屈で足指が使えていないか
- 踵が浮いて安定しない構造ではないか
当院では、インソールや靴のフィッティングも含めた調整を行い、股関節にやさしい歩行環境を整えています。
③ “お尻を鍛える”はNG!正しい順番を守る
「お尻の筋肉を鍛えましょう」と言われて、スクワットや脚上げ運動をしていませんか?
実は、関節の動きが整っていない段階で筋トレをすると、かえって関節に圧迫ストレスを与えることもあります。
安全に筋力を使えるようにするには、
- 骨盤・股関節の位置を整える
- 正しいフォームを学ぶ
- 初めて「筋肉の出番」がくる
この順番を間違えないことが非常に重要です。
靴とインソールで“歩きのクセ”を変える方法
変形性股関節症の進行には、「歩き方のクセ」が密接に関わっています。
そのクセをつくっているのが、実は足の裏の接地パターンや靴の形状だとご存じでしたか?
体を歪ませる“よくある歩き方”
以下のような歩き方をしている方は、知らず知らずのうちに股関節にダメージを蓄積しています:
- つま先が外を向いている(外股歩き)
- 踵から着地せずペタペタ歩く
- 片側ばかり体重をかける
これらは全て、「足裏の感覚が使えていない」「靴が合っていない」ことで起きやすくなる現象です。
インソールは「支え」ではなく「気づきのツール」
整体院導では、市販の硬いサポート用インソールではなく、「感覚入力」を促すタイプのインソールを使用しています。
これは、足裏のどこに重心がかかっているかを“脳にフィードバック”することで、
ご本人が歩きながら自ら修正できるようにするのが目的です。
サポートしすぎない設計が、むしろ自然な再学習を促すのです。
靴も“セミオーダー”でフィット調整
靴そのものも、以下のような点を細かく調整することで、股関節への負担を大きく減らせます:
- ヒールカウンター(かかとの芯)の強さ
- 屈曲位置(曲がるポイント)の適正化
- トゥスプリング(つま先の反り返り)の角度
これらはすべて歩行中の重心移動を正すための重要な要素。
フィット感は「履いてわかる」ものですが、そこに構造の視点を加えることで、
ただの靴選びが「歩き方の再教育」になります。
食事で“軟骨・炎症・筋肉”の回復を早めるには
変形性股関節症の方の多くは、痛み止めや湿布で症状を“抑える”ことに終始しがちです。
しかし、本当の回復には体の内側からの“治す力”の底上げが必要です。
その鍵となるのが、食事=栄養です。
① 軟骨の材料になるタンパク質と抗酸化栄養素
軟骨の主成分はコラーゲンとプロテオグリカン。これらの合成には、
- 良質なタンパク質(肉・魚・卵など)
- ビタミンC(柑橘類・パプリカなど)
- 鉄・亜鉛・マグネシウム(レバー・カキ・ナッツ)
が必要です。
さらに、コラーゲンの質を守るためには、AGEs(糖化最終産物)を増やさない食生活も重要です。
② 慢性炎症を鎮める“油の見直し”
股関節の慢性的な腫れや熱感は、**体内の「炎症状態」**が背景にあることが多いです。
その炎症は、普段の食用油からも影響を受けます。
避けたい油:
- サラダ油(リノール酸過多)
- マーガリン、ショートニング(トランス脂肪酸)
摂りたい油:
- オリーブオイル
- えごま油・アマニ油(オメガ3)
オメガ6とオメガ3のバランスが、炎症の鍵を握っています。
③ 筋肉を“減らさない”ための食タイミング
筋肉量が減ると、股関節の支持力が落ち、痛みの出やすい状態になります。
- 朝食抜き
- 炭水化物だけの食事
- タンパク質の不足
このような食習慣は、**サルコペニア(加齢性筋肉減少)**を加速させます。
特に重要なのは、「朝にタンパク質を摂ること」。
筋合成を刺激し、代謝を活性化させる時間帯です。
整体院導では、京都大学研究員から学んだ超栄養学をもとに、
股関節疾患と栄養の関係を1人ひとりに合わせてご説明しています。
やさしい筋力トレーニングには“パワープレート”
変形性股関節症の患者さんが直面する問題のひとつが、
「運動しなきゃいけないのはわかっているけど、痛くてできない」というジレンマです。
この矛盾を解決するために導入しているのが、**Power Plate(パワープレート)**という振動マシンです。
なぜ振動で筋肉がつくのか?
パワープレートは、1秒間に30〜50回の高速振動を発生させることで、
乗っているだけでも神経と筋肉を同時に刺激し、筋力トレーニング効果を引き出します。
- 体幹の安定性向上
- 股関節周囲の筋肉活性化
- バランス感覚の再教育
これらを短時間・低負荷で実現できるのが最大の利点です。
高齢者にも安全に使える設計
振動の強さは個別に調整できるため、80代の方でも安心して利用可能です。
また、ベッドからの立ち上がりが難しい方には、座位・四つ這い・横向きなどでも使用できます。
「運動はしたいけど、もう無理だと諦めていた」
そんな方にも、もう一度“筋力を取り戻せる希望”を与えてくれます。
週1〜2回でも効果は出る
当院のデータでは、週1〜2回のパワープレート活用で
- 歩行速度が向上
- 階段昇降がラクになる
- 股関節の可動域が拡大する
といった変化が、2〜3ヶ月で現れ始める方も多数です。
当院ならではの“構造”重視の整体とは
多くの整体院や病院では、痛みの出ている場所=股関節にばかり注目しがちです。
しかし、実際には「股関節だけを整えても治らない」ケースがほとんどです。
整体院導では、“構造全体のバランス”を第一に考えた施術を行っています。
「痛みの出ている場所=原因」ではない
股関節の痛みの背景には、以下のような構造の乱れが隠れています。
- 骨盤のねじれ・傾き
- 足首や膝の柔軟性低下
- 背骨の丸まりによる重心のズレ
これらが積み重なることで、股関節に過剰な負担が集中し、軟骨がすり減っていきます。
全身の連動を見ていく施術
導の整体は、「その場しのぎ」ではありません。
- 立位・歩行分析
- 足の接地〜股関節の連動チェック
- 骨盤の可動域テスト
- 肋骨・肩甲骨の動きも確認
こうした全体の構造の崩れを特定したうえで、施術を行います。
一度でスッキリさせるより、“歩ける力”を戻すことが目的
「痛みがゼロになる」よりも大切にしているのは、
自分の足でスムーズに動けるようになること。
そのために、短期間での改善を目指すのではなく、
2〜3ヶ月で歩行距離の回復、半年〜1年で痛みの消失という、現実的かつ再発予防を見据えたプランを提案しています。
ほんの小さな実例をご紹介
ここで、実際に当院へ通われた60代女性のケースをご紹介します。
来院前の状態
3年前から股関節に違和感
最近では500mも歩くと痛みで立ち止まってしまう
整形外科では「変形性股関節症」と診断され、湿布と痛み止めを処方
病院では「年齢的に仕方ない」と言われ、手術はできれば避けたいとの希望あり
当院で行ったこと
InBody計測にて、股関節周囲の筋力低下、むくみ、脂肪蓄積を明確化
靴の選び直しと、かかと重心での歩行指導
パワープレートによる負担の少ない筋力刺激(週1回)
栄養指導では、タンパク質と鉄分不足をサポート
変化の経過(現実的なスパン)
初回〜1ヶ月:歩行後の痛みがやや軽減
2〜3ヶ月:1km以上連続して歩けるように
半年経過時点:階段昇降もラクに。痛みはほぼ消失
本人の声
「どこに行ってもダメだったのに、まさか靴と栄養の見直しでこんなに変わるとは思いませんでした」
「もう歩けなくなると思っていたけど、今は外出が楽しみです」
このように、**“治す”というより“動ける体に戻す”**という視点で取り組むことで、
変形性股関節症にも希望ある未来をつくることができます。
まとめ:変形性股関節症は“歩ける体”を目指せば変わる
変形性股関節症は、
「軟骨がすり減ったからもう治らない」
「年齢のせいだから仕方ない」
と諦められがちな症状です。
しかし、本当の原因は“体の構造の崩れ”や“栄養・運動不足”の積み重ね。
これらを一つずつ見直していくことで、「まだ歩ける未来」は取り戻せます。
整体院 導では、
- 体の構造を整える整体
- パワープレートでの安全な運動刺激
- InBodyによる体内環境の可視化
- 京都大学研究者から学んだ「超栄養学」
- 靴・インソールによる足元からの改善
といった多角的アプローチで、
「どこに行っても治らなかった人」をサポートしてきました。
「どうせ手術しかない…」と諦める前に。
半年〜1年かけて、動ける体に戻すという選択肢を、
あなたの人生に加えてみませんか?
▼公式HPはこちら

▼症状別改善方法やご相談はこちら(初回限定 4,980円)
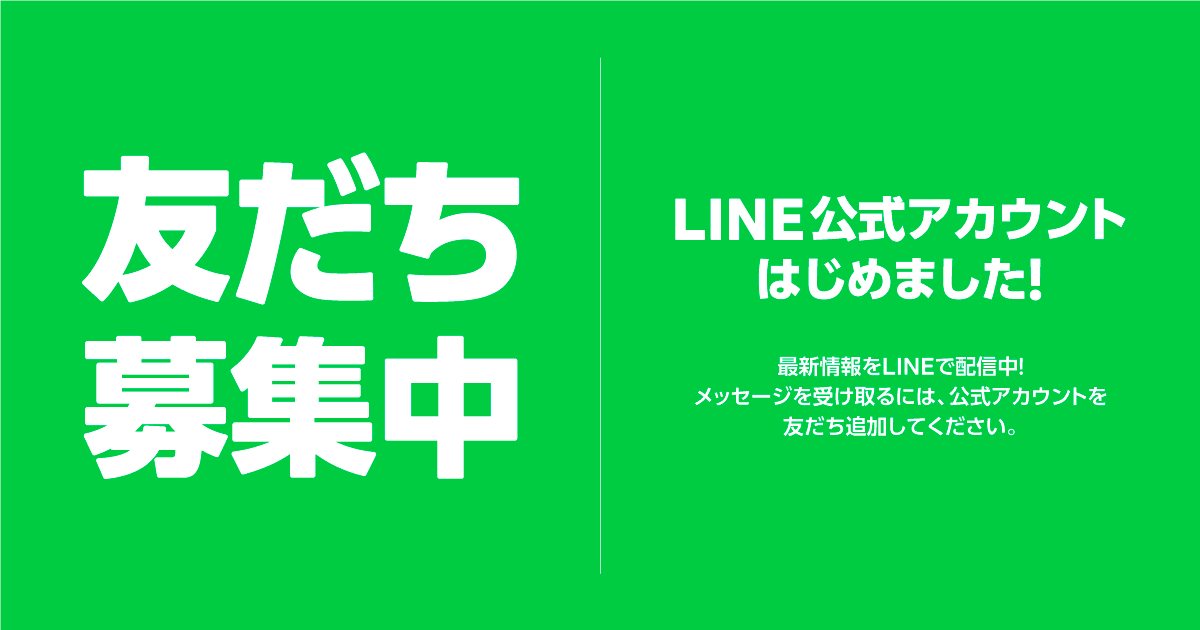

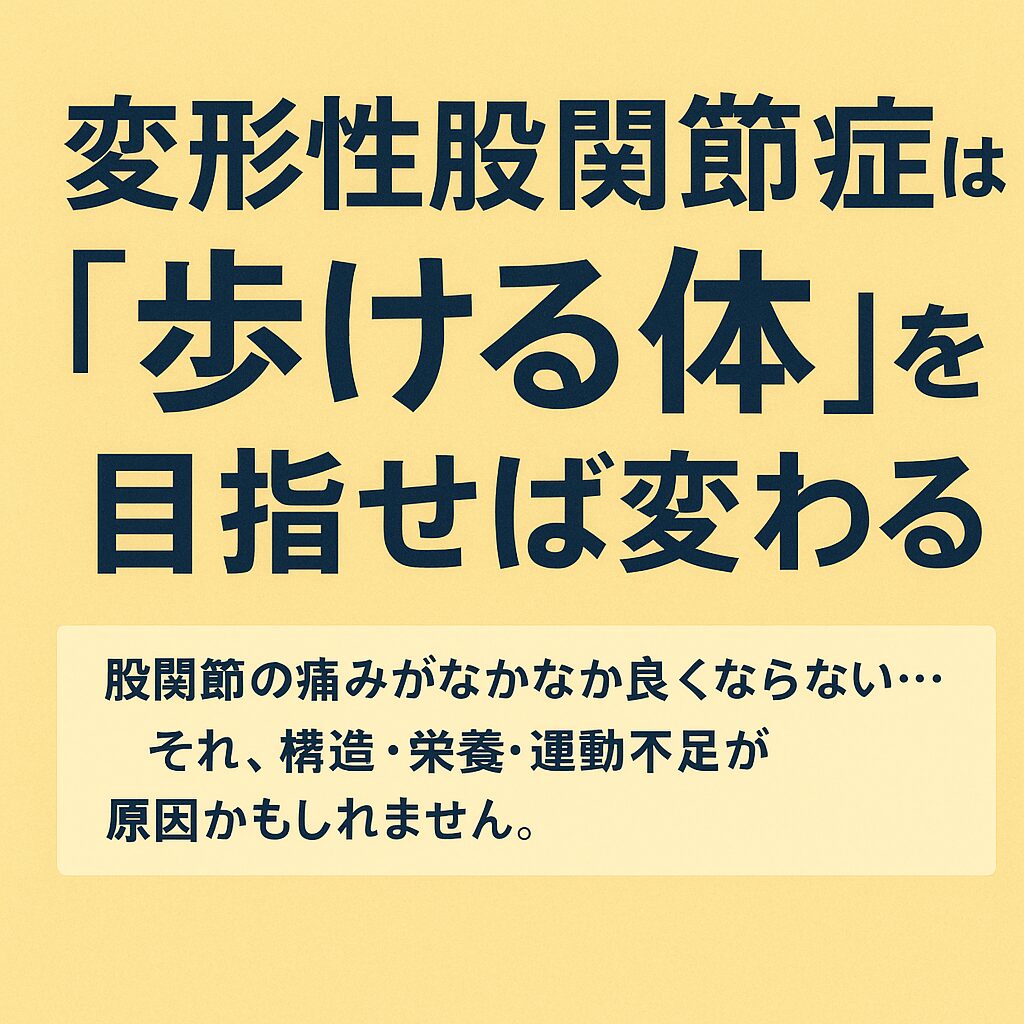
コメント